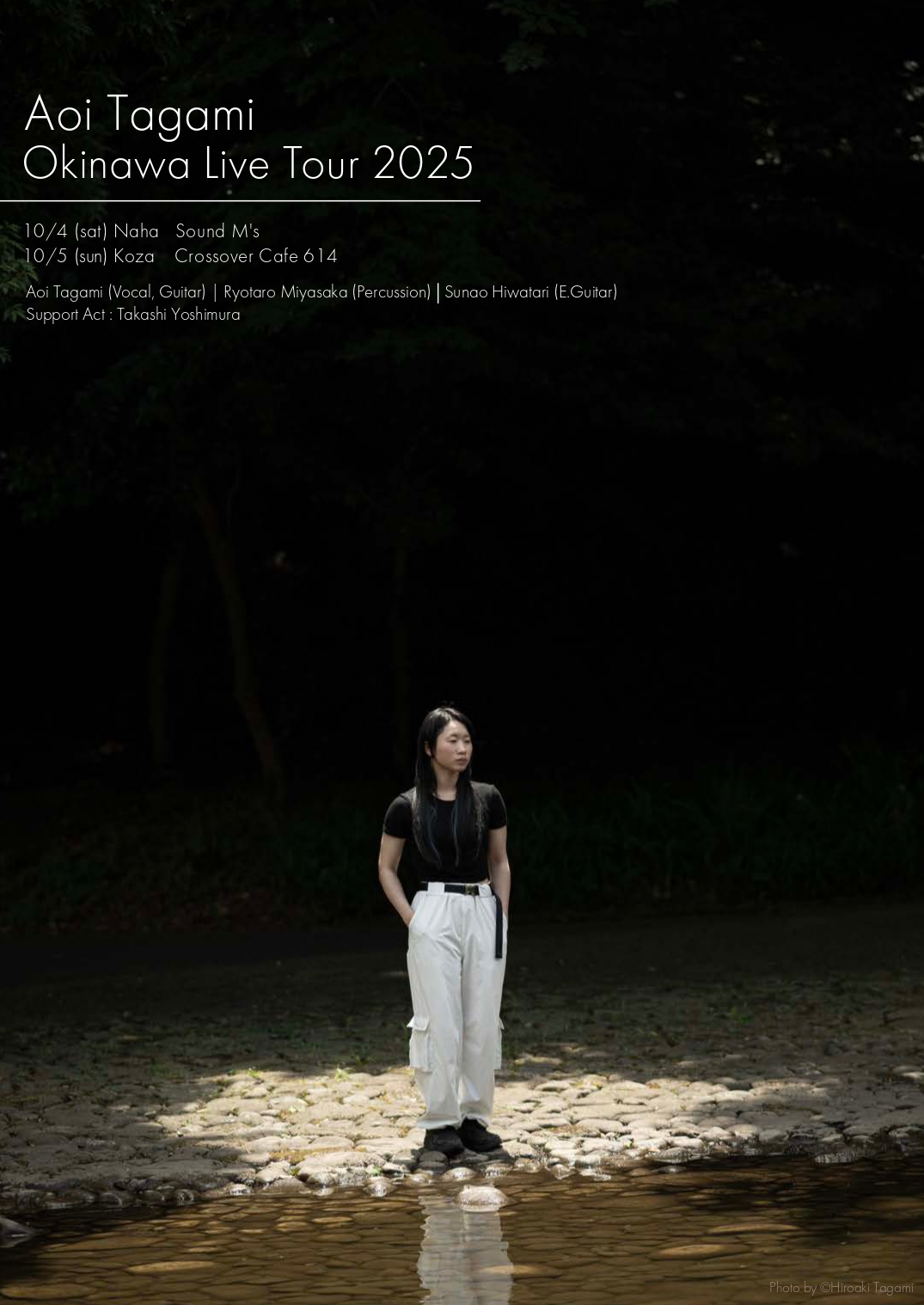“とにかく凄いから、聴いて欲しい、できれば沖縄でライブをブッキングして欲しい”。
この春先、東京の友人に田上碧さんを紹介された。音源を聴いて、彼が連絡をくれた理由がなんとなくわかった。彼女が音楽を通して紡ぐ世界観、しなやかな歌声、自在な即興性に富んだ不思議なアンサンブル、表現される音楽は新しくて美しく、そして深く、私の中で心地よく共鳴した。直感は大切だ。すぐにスケジュールを確認して、10月に沖縄でのライブを決めた。
タイミングが合って、5月に東京でのライブを聴いた。ソロでのパフォーマンスだったが、一瞬で引き込まれてしまう、音源を聴いた印象を超えてくる素晴らしい演奏だった。
今回、沖縄でのライブを前に、田上碧の音楽にまだ触れたことがない人に向けてメールでのインタビューを試みた。
これまでの彼女の活動を俯瞰しつつ、沖縄のことや、そして今後の活動などについて綴ってもらった。
(構成:野田隆司)
************
Q:2014年頃から、“体ひとつで歌う”ことから活動を始められたそうですが、そのスタートに至った背景を教えてください。
「子供の頃からずっと歌を歌うのが好きでした。言葉を声に出すこと自体が好きだったので、一時期は狂ったように音読をしていて、分厚い本を一冊音読で読み切ったり、朗読をMDに録音したりしていました。その後は歌と絵を趣味として10代を過ごし、大学で演劇やコンテンポラリーダンスに出会い、人前に立つようになりました。
当時、自分で作って歌っていたのはセリフに節がついていて歌になったりならなかったりする、一人芝居のような作品でした。上演する空間に生の声を響かせて、その空間の音の響きをその場にいるみんなで再確認するような活動だったと思います。わたしが大きな歌声で詩を叫んだり、声を出しながら走って遠ざかってフェードアウトしていったり…。野外劇やサウンドアートにも影響を受けていました」
Q:即興的に景色を歌と詩にしていく「見て呼ぶ」という独特な手法はどのように生まれたのですか? 実際のライブではどのように展開されていますか?
「2014〜2016年ごろに作っていた一人芝居のような作品は、劇場などではなく野外で発表することが多かった(人が意図して作った響きではなく、偶然そうなっているその場の響きに興味があったため)のですが、続けるうちに、準備してきたセリフや歌の隙間に町や自然の音が入ってくることに気がつきました。そして、自分が作り込んだものよりも、それが演奏・上演される時に現実世界と交わって可視化されるリアルさや偶然性のほうがずっとおもしろいと思うようになった。
たとえば野外でパフォーマンスをした時 “飛行機!” と歌として叫んだら、実際に上空を飛行機が通り過ぎていって、まるで自分が飛行機を呼びこんだみたいになった瞬間がありました。その時に大感動して、こういうことを起こしていきたいと思った。夕方5時のチャイムが作品の中盤で鳴るように計算してパフォーマンスを作ったこともありました。
最近も野外のライブや即興のパフォーマンスなどで “見て呼ぶ” をやることがありますが、基本的にはこれは創作のための、現実と自分がセッションするためのアイディアです」
Q:2019年のインドネシア滞在が即興演奏のきっかけになったとのことですが、現地での体験がどのように現在の表現につながっているか教えてください。
「大きく二つあります。ひとつは、ミュージシャンの方が紹介してくれて、ジョグジャカルタで行われたフリーインプロのライブに出演したこと。インドネシア国外からの出演者も多く刺激的で、こういうことを日本でもやりたいと思うようになりました。
もうひとつ、言葉についての重要な経験をしました。滞在中はインドネシア語で日常生活を送っていたのですが、日本語を話す人が誰もいない場所で生活していると、日本語で描写するということを頼れなくなるんです。感覚的な話ですが、ジャワの木は “木” ではなくて “pohon” だったし、田園風景の美しさは “きれい” じゃなくて “indah” でした。目の前のジャワの景色に日本語が通じない感覚に衝撃を受け、言語や意味よりも、声色やメロディや表情や質感のほうが重要に思えました。そういう戸惑いのなか、現地の楽器屋で買ったアコースティックギターをたくさん弾くうちに、歌を作るようになりました」
Q:2022年以降、自作曲の弾き語りを中心に活動されていますが、これはどんな心境の変化や表現欲求から来たものですか?
「2019年にインドネシア滞在から帰ってから、特殊発声を多用しながら声を楽器のように使って即興の演奏を多くやっていたんですが、言葉を扱う表現も自分にとって大切でしたし、俳優として演劇に出演する機会もこの頃いただいていたので、そこで得た学びも盛り込んでいくと「詩のある歌を書き、ギターを弾きながら自分で歌う」という形が、自分に一番しっくりくるんじゃないかと考えるようになりました。そこで、2020年に『触角が無限にのびる虫』というタイトルの、一人芝居と弾き語りのあいだのような作品を発表しました。(丁寧に録音したものをバンドキャンプでリリースしたので、ぜひお聞きください)
ギターを持って一人で歌う、というフォーマットにのせることで発表の場が増えたし、活動の幅が広くなった気がします。それに、最近ようやく楽器と歌が一つに感じられるようになってきて、ますます楽しいです。
Q:2023年に宮坂遼太郎さん・樋渡直さんと始動したバンド・ガラグアについて、結成のきっかけを教えてください。またこのバンドの中で実感する化学反応のようなものはありますか?
「結成のきっかけは宮坂くんです。一緒に作品を作っていた頃に “田上さんはバンドをやったら良さがもっと出そう” というようなことを言ってくれて、別のバンドで共演したこともあった樋渡くんも呼んで集まって音を出してみたら、めっちゃ音楽だった。二人がいると “歌” だったものが “音楽” になるなあ、という実感があります。二人はそれぞれの自分の言葉のようなものを持っているので、それぞれの思う音楽の方に引っ張ってくれる。でも、まとまるというより、各自が好きに引っ張ってその形に曲が変わるという感じで、いつも冒険の気分です」
Q:音楽・舞台・美術など多ジャンルの作家と協働されていますが、特に印象に残っているコラボレーション体験について教えてください。
「三野新さんという写真家・舞台作家の方とのコラボレーションが印象的です。2023年に十和田市美術館の企画で開催された展覧会で、彼のインスタレーションのなかで再生される音声への出演として、三野さんが書いたセリフをわたしが読んで録るという制作でした。映像にも一部出演しています。出演者はわたしだけで、たくさんの役を演じ分けました。ディレクションによって自分の声が変わっていくのが面白かった。
加えて、展覧会の開催に合わせて演奏しに行ったのですが、この時はいつものような演奏ではなく、三野さんの書いたセリフをライブで朗読しつつ合間に自分の歌を歌う、というものでした。自分の書いた歌の詩の意味が、前後に朗読されるセリフの内容によって違って聞こえることに驚きました。既存の歌が別の文脈で歌われて違う意味を持つ、ということはポップスの歴史のなかで何度もあったことですが、そんな、他人事のように思っていた現象が自分の歌でも起きるんだ、と感動しました」
Q:2024年にリリースした1stアルバム「きらきらするすべて」を通して伝えたかったこと、また制作過程で印象的だった出来事は何ですか?
「かなり短くいえば “世界って捨てたもんじゃない” と伝えたいです。目に見えたり肌で感じたりできる現実世界には、きらきらしている時っていうのがたまにあって、わたしはそういう瞬間を歌にしています。 “こういう目で、世界を見てみるのってどうですか?” という提案みたいな気持ちがあります。
制作過程は、初めてのことばかりで全部おもしろかったのですが、ツバメスタジオの君島結さんと、レコーディングのためのマイクを選んでいた日が思い出深いです。普通、ライブの時には自分の口の前に置いたマイクで声を拾うので “声といえば顔の前で鳴っているもの” と思っていたのですが、その日は、体の後ろ、腰のあたりにマイク立ててみようとか、頭の上の方から録ってみたらどうかなとか、結さんが色々試していて。その時に “田上さんは体で響かせている成分が多い感じがあるのでそういうところも録りたいです” と言っていただき、びっくりしながらすごく嬉しかったです。
ライブで演奏する時と、スタジオで録音する時ってこんなに違うんだ、という驚きもあったし、自分の歌への解像度も上げていただいた気がします。自分の体の骨と筋肉が、どんな形と密度でここにあって、音をどう響かせていくとどうなるのか、については、きっとライブよりもレコーディングのほうがじっくり考えられると思うので、またスタジオでのレコーディング作品を作りたいです」
Q:今回が沖縄での初ライブになりますが、初めての土地でライブをするときに、意識することはありますか?
「なるべく自分の足でひとりで歩くことを意識しています。車で行ったとしても、会場の周りを10分だけ歩くとか、宿泊先の近くを朝歩いてみるとか。すぐに何かになるものではないけど、体にその土地の空気を通すというようなことは大事にしています。
自分が今どこに立っているのか、地図のレベルでもそうですが、東西南北と時間と気候と、そういうことを確認できると、地に足のついた演奏ができる気がしています。地に足がついているといろいろなことに気がつけて良いです。発散というより吸収のほうのベクトルでエネルギーを使うイメージです」
Q:沖縄の文化や自然、音楽シーンから、どのような刺激やインスピレーションを期待していますか?
「まず、植生が見たいです。わたしは、どんな場所へ行く時にもその季節にそこに生えている植物を見るのが好きですが、特に沖縄は、わたしが拠点としている関東地方とは植生が大きく異なるので、木の葉が風にそよぐ音を聞くのも楽しみです。
また、沖縄は歴史も文化も分厚いので、音楽や衣服や料理やお酒や建築など人間の営みの、情報ではなく実際に訪れて触れてみないとわからないところを知りたいです。まずはただ受け取る気持ちで行って、好きな景色を見つけたりしたい。それ以上のことは、流れに身を任せて出会えたものに出会おうという気持ちです」
Q:今後挑戦したい新しい表現やプロジェクトがあれば教えてください。
「バンドをやりたいです。今回一緒に沖縄で演奏する二人とのバンド “ガラグア” も動かしたいし、これまで協働したことのない人との音楽の制作や演奏の機会を増やしていきたいと思っています。具体的には、ずっと使い道を見つけられないでいる声があって “持て余している楽器” という感じなので、それを使える曲が作りたい。自分は真面目すぎるので、そろそろ軽やかな制作をしたいです。
また、歌は可搬性が高く抽象的な表現が得意ですが、同時に、書いて歌う本人にとってはどこまでも具体的であれる、ということが興味深いです。いろいろな場所へ赴いて歌うという活動は、その抽象と具象の行き来の距離をのばし、歌の質を変えて深めてくれるという実感があります。昨年、海外で演奏した時、日本語圏外であっても歌の描くイメージが共有できたりするということにとても希望を感じました。国内外を問わず、いろいろな場所で歌うことは続けていきたいです」
<Live Information>
田上 碧 | Aoi Tagami Okinawa Live Tour 2025
出演
田上 碧 | Aoi Tagami(Vo&G) ・宮坂遼太郎(Per) ・樋渡 直(E.Gt)
サポートアクト:ヨシムラタカシ
<那覇公演>
日程:2025/10/4(土)
会場:Sound M’s(那覇市久茂地3-29-68 久茂地産業ビル3F:国際通り)
時間:開場 18:30 開演 19:00
<コザ公演>
日程:2025/10/5(日)
会場:Crossove Cafe 614(沖縄市中央1-17-15 2F:パルミラ通り)
時間:開場18:30 開演19:00
チケット(2会場共通)
全席自由 :一般前売3,000円 当日3,500円
U-20 前売当日共1,500円
※要1ドリンクオーダー
プレイガイド
Harvestfarm Online Shop(手数料無料)
イープラス
ローソンチケット
予約
H&D:main@handdllc.com
<田上碧 | Aoi Tagami Bio>
ヴォーカリスト。
2014年頃より、野外から劇場空間まで幅広い場で体ひとつで歌うことから活動を始める。歌うことの行為や現象としての側面を浮き彫りにするパフォーマンスや、歌と語りを織り交ぜた楽曲の演奏、景色を即興的に歌と詩にしていく「見て呼ぶ」と名付けた手法を用いた詩作、特殊発声を多用した即興演奏などをおこなう。
2019年に半年間のインドネシア滞在をきっかけに即興演奏を始め、歌・語り・ヴォイスの演奏を織り交ぜた長編の歌『触角が無限にのびる虫』(2020)の発表を経て、2022年からは自作曲の弾き語りを中心に活動中。2023年、宮坂遼太郎・樋渡直と共にバンド・ガラグアを始動。
音楽・舞台芸術・美術などの作家とのコラボレーションワークも多く、近年は、岡千穂、東郷清丸(匚、彡)、マテリアルショップ・カタルシスの岸辺、今尾拓真、涌田悠、三野新らと協働。2024年、1st アルバム『きらきらするすべて』をリリース。